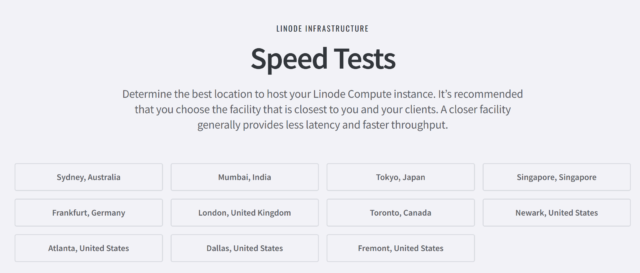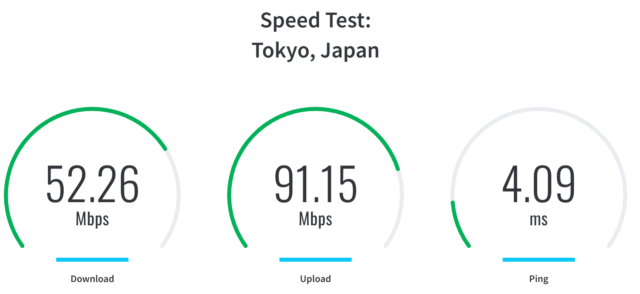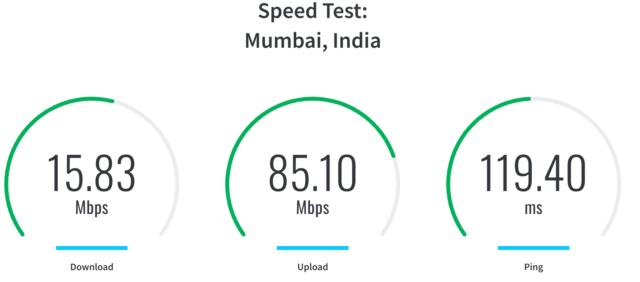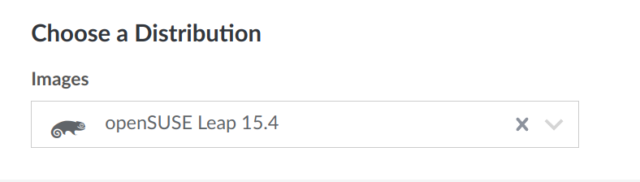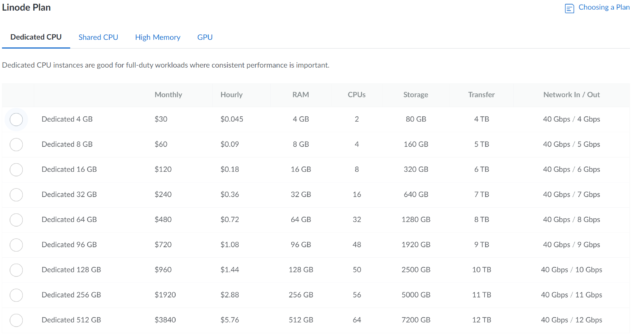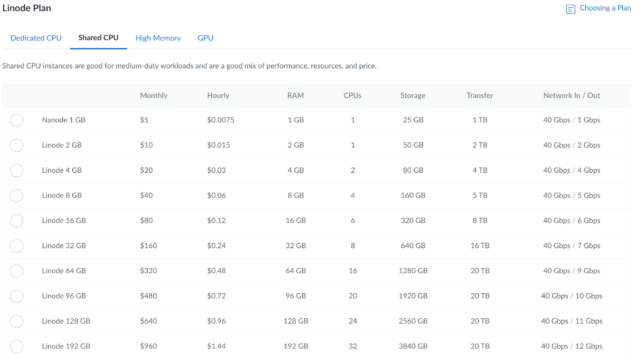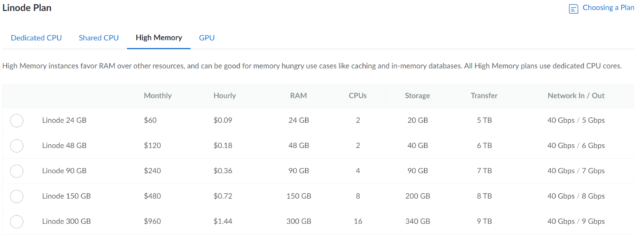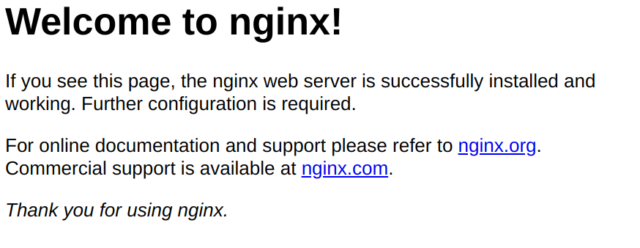By Syuta Hashimoto @
2022-12-15 08:59
この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の15日目です。
CombustionはMicroOSのプリメイドイメージをプロビジョンしてくれるスクリプトです。
ここ数年でMicroOSのプリメイドイメージのプロビジョンソフトが移り変わったので、紹介させて頂きます。
cloud-init
cloud-initはもともとUbuntuのクラウドイメージのプロビジョンソフトウェアでした。MicroOSは初期の頃対応していました。今はOpenStack用のプリメイドイメージ専用になっています。
ignition
CoreOSのプロビジョンソフトウェアで、JSONで記述した設定ファイルを使います。
MicroOSは今もignitionに対応しています。MicroOSのignitionのwikiはこちら です。
Combustion
MicroOS専用のプロビジョンソフトウェアです。スクリプトを書くことで、かなり柔軟な設定をすることが出来ます。dracatモジュールとのことですので、追っていろいろ見てみたいと思います。Combustionのwikiはこちら です。
Category
サーバ ,
仮想化 |
受け付けていません
By Syuta Hashimoto @
2022-12-14 08:54
この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の14日目です。
大分遅くなりましたが、先月、自宅のopenSUSEを15.4にアップデートしました。なお、SLES15 サービスパック3(Leap 15.3のベース)は、2022年12月でサポートが切れる(セキュリティパッチの提供などが終了する)ので、皆さん15.4にアップデートすることをおすすめします。
さて、15.4にアップデートしたところ、emacsを起動した時に初期設定が反映されなくなりました。
そこでXDDCのもくもく会 で力を貸して頂いて対処したので、書いてみます。なお、最終的な解決までには至りませんでした。
結論
/usr/share/hunspell に、ja_JP.affとja_JP.dicを配置する(中身は何でも良い)
症状
emacsを起動しても初期設定が反映されない
*Messages*に以下のメッセージが表示されている
ispell-find-hunspell-dictionaries: Can’t find Hunspell dictionary with a .aff affix file
教えてくださった方法
Ubuntuの開発者の方に、まずstraceでemacs.d/init.el読んでるかみてみたら?と教えて頂きました。
strace -f emacs > strace.log
straceはシステムコールやシグナルをトレースするプログラムです。
このログをinit.elでgrepしても、ヒットしませんでした。なので、そもそもinit.elを読んで無いようです。
どうやら、メッセージにある通り、hunspellの起動が失敗していて、init.elの読み込みまで進んでないようです。
それでhunspellでログをgrepしていると、/usr/share/hunspell/ja_JP.affと/usr/share/hunspell/ja_JP.dicを読みに行く跡がありました。
そこで、/usr/share/hunspell/en_US.affと/usr/share/hunspell/en_US.dicをそれぞれコピーして/usr/share/hunspell/ja_JP.affと/usr/share/hunspell/ja_JP.dicとして配置した所、無事init.elを読み込みました。
hunspellは日本語チェックをする事はないので、このファイルがあることは問題にならないのですが、回避策にしかならないですね・・・
hunspellはどうやらLANGの値を見ているらしく、以下のように起動するとエラーなく起動できました。
LANG=en_US.UTF-8 emacs
hunspellがLANGの値を見る所を探っていけば、根本解決までいけそうですね。
By Syuta Hashimoto @
2022-12-13 08:38
この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の13日目です。
さて、前回 AkamaiさんがLinodeサービスアピールしてますと紹介させて頂いたのですが、各リージョンのスピードテストが出来る場所があったので紹介させて頂きます。
なお、ちゃんとリージョンに日本もありました。
このページ はログインせずとも使えるみたいですね。
日本で測定してみました。
試しに、ムンバイで測定してみました。
それぞれ一回測定しただけなので信憑性は微妙ですが、確かにpingやDLで差が出ていますね。
Akamaiが親会社なので、近いところのリージョンへのアクセスは期待できるのでは無いでしょうか。
Category
サーバ ,
未分類 |
受け付けていません
By ribbon @
2022-12-12 00:49
この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の12日目です。
systemd が使われるようになると、daemon の制御とかのやり方は大きく変わりました。/etc/init.d にあるスクリプトから、systemd パッケージに含まれるコマンドを使うようになってきました。それらのコマンドは、xxxxxctl という、末尾に ctl が含まれるものが多いように感じました。そこで、/usr/bin/ の中にある、末尾が ctl なプログラムがどんなものかを簡単に調べて見ることにしました。
今回は、timedatectl を紹介します。
コマンド名: timedatectl
詳細:
% timedatectl
Local time: 日 2022-12-11 14:27:55 JST
Universal time: 日 2022-12-11 05:27:55 UTC
RTC time: 日 2022-12-11 05:27:55
Time zone: Asia/Tokyo (JST, +0900)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
% timedatectl show
Timezone=Asia/Tokyo
LocalRTC=no
CanNTP=yes
NTP=yes
NTPSynchronized=yes
TimeUSec=Sun 2022-12-11 14:30:45 JST
RTCTimeUSec=Sun 2022-12-11 14:30:45 JST日付の変更もできます。但し、NTP が動作している場合は、一旦 NTP の同期を止めてからでないと変更ができません。ここは date コマンドと違うところです。
# timedatectl set-time "2022-12-11 15:40:00"
Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled
# timedatectl set-ntp no
# timedatectl set-time "2022-12-11 15:40:00"
# timedatectl
Local time: Sun 2022-12-11 15:40:07 JST
Universal time: Sun 2022-12-11 06:40:07 UTC
RTC time: Sun 2022-12-11 06:40:07
Time zone: Asia/Tokyo (JST, +0900)
System clock synchronized: no
NTP service: inactive
RTC in local TZ: no
日付や時刻の変更は、時刻同期機能を入れておけば使う事は少ないと思いますが、date コマンドよりは情報量が多いので、場合によっては便利かもしれません。
Category
Tips ,
サーバ ,
デスクトップ |
受け付けていません
By Syuta Hashimoto @
2022-12-11 14:26
この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の11日目です。
12/4(日)の前日設営と、12/5(月)、6(火)に、Open Source Summit Japan 2022 にボランティアスタッフとして参加してきました。
そこでCDN大手のAkamaiさんがブースを出していて、Linodeというクラウドプロバイダーを買収してクラウドサービスを始めたとアピールされていました。クーポン頂いちゃいました。
そしてなんとそのLinodeのイメージにopenSUSE Leapが入っていました。
(クラウドでサーバー用途で使うならMicroOSがいいですが、さすがに利用者が遠ざかってしまいますかね・・・)
他にも、AlmaLinux、Alpine、Arch、CentOS、Debian、Fedora、Gentoo、Kali、Rocky、Slackware、Ubuntuと、一通り揃っているのでは無いでしょうか。(さすがにミラクルはない模様・・・ここはプッシュのチャンスかも)
お値段はこんな感じです。
Shared CPUだとかなりお安い感じで使えるのでは無いでしょうか。パフォーマンスがどれくらい出るものなのか、興味深いですね。なお、GPUは日本だと選べませんでした。
作成時にsshキーを登録できるので、すぐにssh接続で使えます。IPもグローバルを振ってくれます。
podmanをインストールしてnginxを動かしてみました。
いつも通りの操作で普通に動きました。
せっかくなので、クラウドで遊ぶ時は使わせて頂こうと思います。
あと、各リージョンのベンチマークができるサービスもあったので、後日紹介させて頂きます。
Category
openSUSE ,
未分類 |
受け付けていません
By ribbon @
2022-12-10 10:46
この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の10日目です。
systemd が使われるようになると、daemon の制御とかのやり方は大きく変わりました。/etc/init.d にあるスクリプトから、systemd パッケージに含まれるコマンドを使うようになってきました。それらのコマンドは、xxxxxctl という、末尾に ctl が含まれるものが多いように感じました。そこで、/usr/bin/ の中にある、末尾が ctl なプログラムがどんなものかを簡単に調べて見ることにしました。
今回は、powerprofilesctl を紹介します。
コマンド名: powerprofilesctl
詳細:
% powerprofilesctl list
balanced:
Driver: placeholder
* power-saver:
Driver: placeholder
% powerprofilesctl get
power-saverまた変更は下記のように行えます。
# powerprofilesctl set balanced
# powerprofilesctl get
balancedただ、電源プロファイルを変更することはほとんど無いので、このコマンドの出番はあまりないのかもしれません。
Category
openSUSE ,
Tips ,
サーバ ,
デスクトップ |
受け付けていません
By ribbon @
2022-12-07 21:40
この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の5日目です。
systemd が使われるようになると、daemon の制御とかのやり方は大きく変わりました。/etc/init.d にあるスクリプトから、systemd パッケージに含まれるコマンドを使うようになってきました。それらのコマンドは、xxxxxctl という、末尾に ctl が含まれるものが多いように感じました。そこで、/usr/bin/ の中にある、末尾が ctl なプログラムがどんなものかを簡単に調べて見ることにしました。
今回は、hostnamectl を紹介します。
コマンド名: hostnamectl
詳細:
Static hostname: suse154
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 61ee5253e44f403c9918308e232c84b8
Boot ID: 2dc4f7eae3724c6497708a64e08a516c
Virtualization: kvm
Operating System: openSUSE Leap 15.4
CPE OS Name: cpe:/o:opensuse:leap:15.4
Kernel: Linux 5.14.21-150400.24.33-default
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: QEMU
Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_と、たくさんの情報を表示します。今回テストしている環境が KVM 配下であることもバレてしまいます。旧来の hostname コマンドと互換を取るには、引数として hostname を指定すれば良いです。単に hostname を返します。
# hostnamectl hostname suse154A
# hostnamectl hostname
suse154Aそのほかに、JSON形式で出力することも可能です。
hostnamectl --json=pretty
{
"Hostname" : "suse154",
"StaticHostname" : "suse154",
"PrettyHostname" : null,
"DefaultHostname" : "localhost",
"HostnameSource" : "static",
"IconName" : "computer-vm",
"Chassis" : "vm",
"Deployment" : null,
"Location" : null,
"KernelName" : "Linux",
"KernelRelease" : "5.14.21-150400.24.33-default",
"KernelVersion" : "#1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 4 13:55:06 UTC 2022 (76cfe60)",
"OperatingSystemPrettyName" : "openSUSE Leap 15.4",
"OperatingSystemCPEName" : "cpe:/o:opensuse:leap:15.4",
"OperatingSystemHomeURL" : "https://www.opensuse.org/",
"HardwareVendor" : "QEMU",
"HardwareModel" : "Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_",
"ProductUUID" : null
}JSON 形式で出力する場合、hostname オプションを指定すると、json 機能は無効になってしまうようです。
従来からの hostname コマンドもたぶん残っていくとは思いますが、新しい hostnamectl コマンドも覚えて置いた方が良いかもしれません。
Category
openSUSE ,
Tips ,
サーバ |
受け付けていません